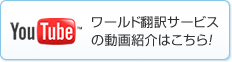バイリンガル教育に思う ~本当に大切なこと~
2025年4月24日 16時25分
以前、バイリンガル教育について、弊社のイギリス人校閲者が記した記事をご紹介しました。
校閲者は、お子さんを英語と日本語のバイリンガルに育てた経験を語ってくれましたが、
筆者の家庭もバイリンガル環境で子育てをしているため、
彼が書いた記事には共感するところが多く、大変興味深く読みました。
今回の記事では、筆者がバイリンガル教育に対して思うことを
実体験を交えながら記したいと思います。
(バイリンガル教育については様々な意見があるかと思います。
一個人の感想としてお読みいただければ幸いです。)
校閲者は、お子さんを英語と日本語のバイリンガルに育てた経験を語ってくれましたが、
筆者の家庭もバイリンガル環境で子育てをしているため、
彼が書いた記事には共感するところが多く、大変興味深く読みました。
今回の記事では、筆者がバイリンガル教育に対して思うことを
実体験を交えながら記したいと思います。
(バイリンガル教育については様々な意見があるかと思います。
一個人の感想としてお読みいただければ幸いです。)
バイリンガル教育の基本ルール「一人一言語」とは?
まずは、筆者の家庭のバックグラウンドからご説明します。
・居住地:日本
・母(筆者):日本語ネイティブ、語学スキル→ポルトガル語・英語
・父:ポルトガル語ネイティブ、語学スキル→英語・初級日本語
・子:3歳(保育園は日本語環境)
夫婦間の会話はポルトガル語ですが、
親子のコミュニケーションは基本的に”OPOL”という方法で行っています。
OPOLはOne Person, One Language(One Parent, One Language)の略語で、
日本語では一人一言語、一親一言語などと呼ばれています。
両親(または日常的に子どものお世話をする人)の母国語が異なる場合、
それぞれが自分の母国語だけを一貫して子どもに話しかけるというメソッドです。
・居住地:日本
・母(筆者):日本語ネイティブ、語学スキル→ポルトガル語・英語
・父:ポルトガル語ネイティブ、語学スキル→英語・初級日本語
・子:3歳(保育園は日本語環境)
夫婦間の会話はポルトガル語ですが、
親子のコミュニケーションは基本的に”OPOL”という方法で行っています。
OPOLはOne Person, One Language(One Parent, One Language)の略語で、
日本語では一人一言語、一親一言語などと呼ばれています。
両親(または日常的に子どものお世話をする人)の母国語が異なる場合、
それぞれが自分の母国語だけを一貫して子どもに話しかけるというメソッドです。
バイリンガル教育が一筋縄では行かない理由
今のところ、我が子は日本語とポルトガル語(時に英語)を器用に使い分けていますが、
今後、子どもの成長過程や周囲環境の変化に伴って、
優勢言語のバランスが変わる可能性もあると思いますし、
「国際結婚 = 子どもはバイリンガル」という図式は、
簡単に成り立つものではないことを実感しています。
多言語環境で子どもを育てる多くの人が感じていることと想像しますが、
子どもの言語発達には、周囲の環境、親子の関係性、子ども自身の興味や性格など、
いろいろな要素が複雑に影響するため、
それに対する親の理解や努力は欠かせないものと思います。
また、それぞれの家庭によって状況が異なるのも当然と認識しています。
将来の計画(どこに住み、何語で教育を受けるのか)次第で、
どの言語を優先すべきか決める場合もあるかもしれません。
今後、子どもの成長過程や周囲環境の変化に伴って、
優勢言語のバランスが変わる可能性もあると思いますし、
「国際結婚 = 子どもはバイリンガル」という図式は、
簡単に成り立つものではないことを実感しています。
多言語環境で子どもを育てる多くの人が感じていることと想像しますが、
子どもの言語発達には、周囲の環境、親子の関係性、子ども自身の興味や性格など、
いろいろな要素が複雑に影響するため、
それに対する親の理解や努力は欠かせないものと思います。
また、それぞれの家庭によって状況が異なるのも当然と認識しています。
将来の計画(どこに住み、何語で教育を受けるのか)次第で、
どの言語を優先すべきか決める場合もあるかもしれません。
多言語家庭として 試行錯誤の日々
我が家の場合、いろいろな方法を試して行き着いたのが”OPOL”ですが、
最初はどのようなやり方がベストなのか分からず、
インターネットで調べたり、知り合いの多言語家庭に意見を聞いたりもしました。
筆者にとって特に気がかりだったのは、
日本に住み、平日は日中の大半を保育園で過ごす我が子は
必然的に日本語を使う時間が長くなるため、
ポルトガル語が不得意になるのではないかということでした。
言語文化が子どものアイデンティティ形成に与える影響なども考慮しましたが、
「国際結婚で生まれた子として、2つの言語を出来るようになってほしい」
という親としての願いが何よりも強かったように思います。
筆者の母国語は日本語ですが、ポルトガル語も話せるため、
「自宅では自分もポルトガル語で子どもに話しかける」
「ただし、家の外にいる時は日本語で話しかける」というルールを作るなど、
ポルトガル語の強化を目指して、いろいろな方法を試した時期もありました。
しかし、細かく線引きをすると親の立場としてもやりづらく、
子ども側も混乱するのではないかという不安が生まれました。
こうして、正解が分からずにしばらく悩む日々が続いたのですが、
ある日、多言語環境の家庭をサポートする機関の方に
自分の悩みを相談する機会をいただきました。
最初はどのようなやり方がベストなのか分からず、
インターネットで調べたり、知り合いの多言語家庭に意見を聞いたりもしました。
筆者にとって特に気がかりだったのは、
日本に住み、平日は日中の大半を保育園で過ごす我が子は
必然的に日本語を使う時間が長くなるため、
ポルトガル語が不得意になるのではないかということでした。
言語文化が子どものアイデンティティ形成に与える影響なども考慮しましたが、
「国際結婚で生まれた子として、2つの言語を出来るようになってほしい」
という親としての願いが何よりも強かったように思います。
筆者の母国語は日本語ですが、ポルトガル語も話せるため、
「自宅では自分もポルトガル語で子どもに話しかける」
「ただし、家の外にいる時は日本語で話しかける」というルールを作るなど、
ポルトガル語の強化を目指して、いろいろな方法を試した時期もありました。
しかし、細かく線引きをすると親の立場としてもやりづらく、
子ども側も混乱するのではないかという不安が生まれました。
こうして、正解が分からずにしばらく悩む日々が続いたのですが、
ある日、多言語環境の家庭をサポートする機関の方に
自分の悩みを相談する機会をいただきました。
言語習得より大事なこと 親が自分の母国語を大切にすべき理由
その機関の専門家の方からご教示いただいたアドバイスは、
自分のなかで非常に大きな気付きとなりました。
それは、言語の使い分けのルールよりも、親子が楽しく、心地よく会話をしながら、
コミュニケーションを育むのが第一優先であるということ。
そのためには、
「親が自分の思いや気持ちを最も込められる言語(=それぞれの母国語)で
子どもと関わっていくことをぜひお勧めしたい」という提案でした。
ポルトガル語は得意でも、母国語が日本語である筆者にとって、
子どもとポルトガル語で話すことにぎこちなさを感じたのは何故なのか——
「この葉っぱ、とげとげしてるね」
「この石はごつごつだね」
日本語独特のオノマトペを使いながら子どもと話すとき、
どうして心が満たされるような気がしたのか——
「一親一言語」は子どもが言語を混同しないための手段と捉えていましたが、
「”親自身”が自分の”最も豊かな言語”で子育てをするための方法でもある」
という考えを教えていただき、ストンと腑に落ちたのです。
自分のなかで非常に大きな気付きとなりました。
それは、言語の使い分けのルールよりも、親子が楽しく、心地よく会話をしながら、
コミュニケーションを育むのが第一優先であるということ。
そのためには、
「親が自分の思いや気持ちを最も込められる言語(=それぞれの母国語)で
子どもと関わっていくことをぜひお勧めしたい」という提案でした。
ポルトガル語は得意でも、母国語が日本語である筆者にとって、
子どもとポルトガル語で話すことにぎこちなさを感じたのは何故なのか——
「この葉っぱ、とげとげしてるね」
「この石はごつごつだね」
日本語独特のオノマトペを使いながら子どもと話すとき、
どうして心が満たされるような気がしたのか——
「一親一言語」は子どもが言語を混同しないための手段と捉えていましたが、
「”親自身”が自分の”最も豊かな言語”で子育てをするための方法でもある」
という考えを教えていただき、ストンと腑に落ちたのです。
紆余曲折を経て、バイリンガル教育に思うこと
現在、筆者の家庭の生活基盤は日本のため、
今後も子どもがポルトガル語を継続的に上達していけるか、
不安がないわけではありません。
しかし、その懸念については、ポルトガル語ネイティブである父親が
子どもと楽しく、心地よく関わっていけば、
ポルトガル語を使いたいという本人の意欲に繋がる、
と専門家の方に教えていただき、
いちばん大切にすべきことを見つけられたように思います。
昨今、グローバル化が進むなかで、子どもが小さいうちから
英語などの外国語教育に力を入れているご家庭も多いかと思います。
実際に、我が子が通う保育園も年少から英語の授業が始まり、
家庭内でも英語のコンテンツなどを見せることがあります。
世間的に早期教育を促す風潮が強いことも関係しているかもしれませんが、
英会話教室に行ったり、英語の通信教材を使ったり、
幼少期から英語を学ばせることは一般的なトレンドになったと感じます。
早くから子どもを外国語に触れさせることについては、個人的には賛成です。
しかし、教育に熱が入るあまり、本当に大切なことを忘れてはいけない、
そう感じた自分の経験を皆さんにもシェアしたいと思い、
この記事を書くに至りました。
子どもの外国語学習やバイリンガル教育について悩んでいる方にとって、
筆者の体験が少しでも参考になれば幸いです。

今後も子どもがポルトガル語を継続的に上達していけるか、
不安がないわけではありません。
しかし、その懸念については、ポルトガル語ネイティブである父親が
子どもと楽しく、心地よく関わっていけば、
ポルトガル語を使いたいという本人の意欲に繋がる、
と専門家の方に教えていただき、
いちばん大切にすべきことを見つけられたように思います。
昨今、グローバル化が進むなかで、子どもが小さいうちから
英語などの外国語教育に力を入れているご家庭も多いかと思います。
実際に、我が子が通う保育園も年少から英語の授業が始まり、
家庭内でも英語のコンテンツなどを見せることがあります。
世間的に早期教育を促す風潮が強いことも関係しているかもしれませんが、
英会話教室に行ったり、英語の通信教材を使ったり、
幼少期から英語を学ばせることは一般的なトレンドになったと感じます。
早くから子どもを外国語に触れさせることについては、個人的には賛成です。
しかし、教育に熱が入るあまり、本当に大切なことを忘れてはいけない、
そう感じた自分の経験を皆さんにもシェアしたいと思い、
この記事を書くに至りました。
子どもの外国語学習やバイリンガル教育について悩んでいる方にとって、
筆者の体験が少しでも参考になれば幸いです。